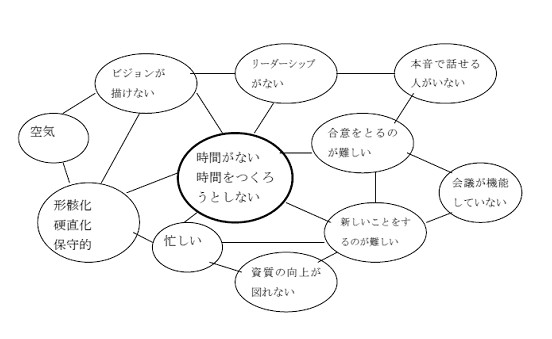先週の話題「『ありがとう、さようなら』を読んで」についてコメントします。
私もこの記事を見るまで、この本のことは知りませんでした。
早速、取り寄せて読んでみました。
「しかし、よくも悪くも、日本人が書く学校というのはこのレベルなんだろうな~、と思わされました。 何も変わっていかない、ということも含めて。」
➡読んでみて、パートナーがこのような感想を抱いた理由が理解できました。
彼女の目はあくまでも作家の目や、なりたい教師になって満足している教師の目であって、よりよいものを子どもたちに提供することに生きがいを感じる教師の目ではないのです。
➡書かれている内容は、ほとんどすべてが授業以外の話です。体育祭、文化祭、修学旅行といった学校行事の様子や生徒会など。確かに、学校行事等で盛り上がったり、生徒と一緒に何かを作り上げたりするという面白さはあると思います。学校行事が果たす役割も重要です。しかし、授業以外は所詮脇役なのです。やはり主役は日々の授業。この授業の楽しさや面白さが語られなければ、学校教育を語ったことにはならないでしょう。
たとえば、理科の授業で目の前で起きた現象の裏側の「目に見えない」原理や法則がわかったときの不思議さや面白さ。歴史の授業で、歴史的な出来事の背景にある人々の苦悩や葛藤、思い、不条理なことなどを知ること。そのような場面を仲間とともに学ぶ喜び。あるいは生徒とともに、また保護者や地域の人々のサポートを得ながら学習活動を展開していく授業づくり。本来ならば、そのような授業の場面こそ、学校をテーマにした物語に相応しいと思います。
『ありがとう、さようなら』のような本が、世に出る仕組みや構造(=日本の出版のあり方やそれを取り巻く社会のあり方)まで考えさせられてしまいました。
➡授業づくりに関係する翻訳本などを出版することの難しさを知ると、今の出版業界のあり方について考えさせられます。
物理教育に長年携わっていた川勝 博さんが書かれた「理科教育法講義」(海鳴社2016)には、理科のカリキュラムづくりに取り組む教師や教師志望の学生たちの様子が描かれていますが、そのような取組が学校の中でもっと広まっていくといいなと思います。
※この文章を書きあげた後に、レイフ・エスキス「教師としていちばん大切なこと」を手にすることができたので、少し読み始めました。こちらはやはり授業の中での子供とのやりとりや子供たちのためにどんなことができるのかを懸命に追究した教師の物語が描かれています。彼我の差は大きいです。